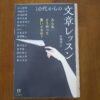もう、ずいぶん昔のことになります。
子どもが、学校に行けなくなった日。
それまで快活だった子が、しゃべらなくなり、笑わなくなりました。
話しかけても、わずかに目を動かすだけ。
同年代の子よりも語彙が豊富で、言葉でのコミュニケーションがとりやすい子だったのだけれど、
まるで言葉の通じない相手になったようでした。
暴れたり叫んだりするわけじゃないのです。
ただ、何を言っても、ほとんど反応がありません。
反応がない子どもに、私は伝え続けていました。
労りや心配の気持ち、一般的な主義主張、向き合って得た気づき、他愛のない雑談…
いろんなことを話し続けました。
「伝え続ければ、伝わる」と、思っていたんです。
自分の気持ちや考えを、丁寧に言葉にすれば、相手にもきっと届く。
そう信じていたし、そうあってほしいと願っていました。
でも、学校に行けなくなった子供と向き合う時間は、それとはまったく別次元の場所だったのです。
学校に行けない理由がわからない。
問いかけても、答えが返ってこない。
今、目の前にいる子どもが、何を感じているのかすらわかりません。
言葉ではたどり着けない感情に、何度も何度も、とまどいました。
やがて私は、言葉の手前にあるものを、見つめるようになりました。
まなざしの先、わずかに動く表情。
長い沈黙、震えるように小さなしぐさ。
「どうして伝わらないんだろう」という焦りとも、何度も向き合うことになりました。
この子のことを、なんとか理解したいと思いました。
そうして、気がついたのです。
私の「伝えたい」は、「私の言葉で、相手を変えたい」だったことに。
私の「わかりたい」は、「私の知る言葉に、相手を収めたい」だったことに。
なんて身勝手な、言葉の使い方だったのか。
人は人、自分は自分。
そのあいだに橋をかけるのが、言葉だとしても。
無理に渡らせるものではなくて、
ただ「ここにあるよ」と、示すだけでよかったんです。
その言葉のコミュニケーションを受け取るかどうかは、相手の自由だから。
何も答えがなくてもいい。わからないことは、わからないままでもいい。
私の言葉のルールを、子どもが受け入れなければならないなんて、決まりはありません。
逆もまた同じ。
子どもと過ごす日々の中で、私は、
「伝えるための言葉」よりも、「ともにいるための言葉」を選ぶようになりました。
違いを認めるための強さという、やさしさを教えてもらいました。
子どもが「私とはちがう存在」であることを、自然に受け入れられたとき。
豊かな語彙と表情を取り戻した子どもは、前よりもずっと、言葉で語り合える相手になったのです。
あの頃の感覚は、私の文章に、静かに息づいています。
押しつけていないか。閉じていないか。
感覚を研ぎすませて、確かめています。
子どもと向き合うように。
言葉とも、読んでくれる人とも、まっすぐに向き合うために。